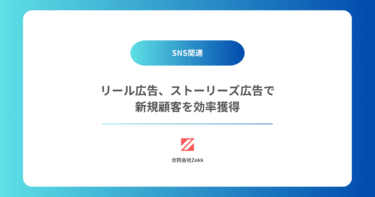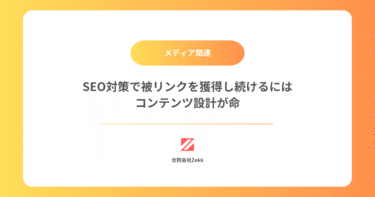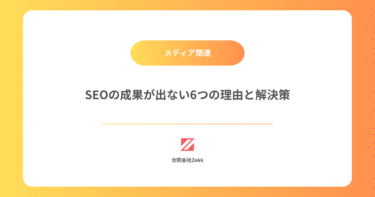オウンドメディアの運営や企業サイトのアクセス解析を始めると、まず多くの方が混乱してしまうのが「セッション数」「PV数」「ユーザー数」といった指標の違いではないでしょうか。記事を何度もリライトして、SNSでも宣伝をしているのに思うように結果が出ない――そうした状況に置かれたとき、どの数字を追いかければいいのか分からず、分析や改善の施策を打つにも手が止まってしまいがちです。
特に経営者や個人事業主であれば、限られたリソースの中で効果的なマーケティング施策を実施したいところです。しかし、「セッション数は増えたけれどPV数はさほどでもない」「ユーザー数が減ったのにセッション数は維持している」といったアクセス解析ツールの指標を正しく理解できていなければ、戦略や施策に一貫性が生まれず、思うようにコンバージョン(問い合わせや資料請求などの行動)につなげられません。
本記事では、「セッション数とは?」という基本的な定義から、PV数(ページビュー数)、ユーザー数(ユニークユーザー数)との違いをわかりやすく解説していきます。さらに、実際のオウンドメディア制作・運営の現場でどのように分析を行い、改善していくのが望ましいかについても、具体的な事例や指標の見方を交えながら詳しく取り上げます。記事を最後までお読みいただくことで、アクセス解析の基礎知識をしっかりと身につけていただき、Webサイトやメディアの成果向上に役立つ視点とノウハウが得られるはずです。限られた人員や予算の中でも、正しい指標を理解し、効率よく成果を出すためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
セッション数・PV数・ユーザー数の基礎をしっかり理解しよう
Webサイトやオウンドメディアを運営するうえで、アクセス解析ツールを用いることはもはや当たり前です。その代表的なツールである「Google アナリティクス」では、ダッシュボードにさまざまな指標が表示されます。しかし、これらの指標を正しく捉えないまま漫然と数値を眺めていても、具体的な改善策や企画のアイデアに結びつけるのは難しいでしょう。ここでは、アクセス解析の基礎となるセッション数・PV数(ページビュー数)・ユーザー数の定義を再確認し、それぞれが示す意味を明確にします。
セッション数とは何か?
「セッション数」とは、ユーザーがあなたのサイトやメディアを訪問し、一定期間内に行った行動(閲覧、ページ移動、コンバージョンなど)をひとまとまりとして数えた単位です。たとえば、Aさんが朝9時にあなたのサイトを訪れ、10分間ほど滞在して複数ページを閲覧し、いったん離脱したとします。そして、同じ日の午後2時に再び訪問した場合、Google アナリティクスの基準では「2つのセッション」とカウントされるわけです。
セッションの定義はアクセス解析ツールによって多少異なる場合がありますが、Google アナリティクスの場合は基本的に以下の2つの条件でセッションが終了すると考えられています。
- ユーザーの一定時間の操作がない場合(デフォルトでは30分)
- 日付が変わったタイミング
セッション数が増えているということは、複数回の訪問や長めの滞在がある可能性が高いと言えます。しかし、単にセッション数が多いからといって必ずしもビジネス成果につながるわけではありません。どのような目的でサイトを訪れ、どんな行動をとったのか、他の指標と組み合わせてみることが重要です。
PV数(ページビュー数)との違い
一方、PV数(ページビュー数)はその名のとおり「閲覧されたページの総数」を指します。先ほどのAさんの例でいうと、最初の訪問(セッション)でAさんが5ページ閲覧し、次の訪問で3ページ閲覧したとすれば、合計で8PVとしてカウントされます。
セッション数とPV数はよく混同されがちですが、以下のように区別できます。
- セッション数:サイトを訪問した“回数”
- PV数:訪問中に閲覧された“ページの総数”
つまり、1回のセッション内で複数ページを閲覧すれば、そのセッション数は1でもPV数は複数となるわけです。閲覧者が多くのページを回遊しているサイトは、セッション数よりもPV数がより大きくなることがほとんどです。
ユーザー数(ユニークユーザー数)との関係
「ユーザー数(ユニークユーザー数)」は、一定期間内にあなたのサイトを訪れた“固有の訪問者数”を指します。たとえば、同じ人物が1日に3回アクセスしてきても、ユーザー数は1ですが、セッション数は3、PV数は閲覧ページ数に応じて増えることになります。
- ユーザー数:ユニークな訪問者(デバイスやブラウザ単位でカウントされる)
- セッション数:訪問の回数
- PV数:閲覧ページの総数
このように、それぞれが示す意味は微妙に異なるため、オウンドメディアや企業サイトの目的次第で、どの指標を重点的に見るべきかが変わってきます。たとえば、認知度向上を目的としているならユーザー数の増加が望ましいですし、詳細情報を多く読んでもらって商談や問い合わせにつなげたいならセッション数やPV数の深掘りが重要になる場合もあります。
なぜセッション数・PV数・ユーザー数の違いを理解する必要があるのか
アクセス解析を行う際、多くの方は「数値が多ければ嬉しい」と考えがちです。しかし、やみくもに指標を追いかけるだけでは、真に改善すべきポイントが見えず、施策が空回りすることもあります。ここでは、それぞれの指標を正しく理解するメリットと、ビジネスやマーケティング全体に与える影響を考えてみましょう。
施策立案と予算配分が最適化できる
たとえば、メディアの滞在時間が長く、PV数はそこそこある一方で、ユーザー数がそれほど伸びていない場合は、新規集客や認知拡大を強化する必要があるかもしれません。また、セッション数は多いがPV数が少ない場合は、サイト内での回遊性が低い可能性があります。こうした状況把握があれば、どこにリソースを集中すべきかが見えてきます。
- 集客施策(広告出稿やSNS運用など):ユーザー数の増加を目的に配分
- サイト内施策(UI/UX改善、コンテンツ拡充など):PV数や直帰率改善を目的に配分
指標を細分化して追うことで、次に打つべき施策とその予算配分を最適化しやすくなります。
ターゲット読者(顧客)の行動を深く分析できる
セッション数が増えても滞在時間が短かったり、直帰率が極端に高かったりする場合は、コンテンツの内容やページ遷移の導線に問題がある可能性があります。逆に、PV数が高くてもセッション数が少ない場合は、一部のヘビーユーザーが何度も繰り返し同じサイトを閲覧しているだけというケースも考えられます。
セッション数、PV数、ユーザー数を横断的に見ることで、「新規ユーザー」と「リピーター」の違いや、「どのページからサイトを離脱しているのか」といった行動パターンをより深く解析できます。
KPI・KGIの設定が明確になる
ビジネスにおいては、最終的に「売上や問い合わせ件数が増えること」を目指しているケースが多いでしょう。Webサイトやオウンドメディアにおいても、KPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)を設定する際、それぞれの数値を基に逆算して考える必要があります。
- 例1:問い合わせフォームへの誘導が目的 → 「セッション数」よりも「CVR(コンバージョン率)」と「ユーザー数」が重要
- 例2:情報リテラシーやブランド認知度向上 → 「ページの滞在時間」や「PV数」、特定のカテゴリー閲覧率が重要
指標をしっかり理解していれば、KPI設定や成果分析の精度が高まり、サイト全体の最適化を進めやすくなるのです。
オウンドメディア運営でのセッション数活用法
オウンドメディアを運営する場合、コンテンツの量や質を高めるだけでなく、どんな人がどのように訪問しているのか、そこからどう行動を起こしているのかを把握することが大切です。セッション数はユーザーとの接触機会を測る指標として便利ですが、数値を追うだけでなく、その背景にある読者の動機や興味を読み取ることが鍵になります。
コンテンツの評価指標としてセッション数をチェックする
新たに記事を公開したときやリライトを行ったとき、あるいはSNSで拡散を試みたときなど、セッション数の変化を見れば、ユーザーがどの程度興味をもってサイトに訪れているかがおおまかに分かります。
一時的なキャンペーンなどで流入を増やすのも一つの戦略ですが、重要なのは「継続的にセッション数を維持・増やせるコンテンツ構成」を目指すことです。短期的に伸びてもすぐに戻ってしまうのであれば、根本的な改善策を考える必要があります。
ユーザーの回遊パターンを掴む
セッション数が増えているのにPV数や滞在時間が伸びていない場合、読者はすぐに離脱している可能性が高いです。これはタイトルやリード文が魅力的でクリックはされるものの、中身に期待した情報がなかったり、読みやすい構成になっていないことが原因かもしれません。
また、セッション数とPV数がともに増えているのであれば、記事やサイト内のリンク導線がうまく機能していると考えられます。カテゴリ別やタグ別の移動、関連記事への誘導などを整備して、ユーザーが複数ページを閲覧したくなる仕掛けを意識することが重要です。
SNS流入・検索流入別の傾向を把握する
オウンドメディアへ流入する経路は、大きく分けると検索エンジン経由(オーガニックサーチ)とSNS経由、直接流入(ブックマークやURL直打ち)などがあります。それぞれの流入元によって、ユーザーの属性や興味関心が異なることは珍しくありません。
たとえば、SNS経由のユーザーは拡散力が高い一方、興味がなければすぐに離脱しがちです。セッション数の伸びが一時的に大きい場合、SNSでバズっている可能性がありますが、回遊を促す導線が弱いと離脱が早まり、PV数や滞在時間が期待ほど伸びないことがあるでしょう。
一方、検索流入では、特定のキーワードで興味をもってやってくるので比較的深い閲覧が期待できますが、検索意図に合わないコンテンツだと直帰率が高くなる可能性もあります。セッション数を入り口に、流入経路別の行動を分析することで、より適切なコンテンツ設計と運営体制を構築することができます。
セッション数を増やす具体的な施策と注意点
セッション数を増やすためには、「新規ユーザーを呼び込む施策」と「リピーターを増やす施策」の両面からアプローチするのが効果的です。しかし、ただ数を追うだけでなく、成果指標(問い合わせ、資料請求、SNSフォローなど)を念頭に置きながら最適化を進めることが大切です。ここでは、具体的な施策例を見ていきましょう。
SEO対策の強化で検索流入を拡大する
検索エンジンからの流入を増やすことは、オウンドメディア運営において最もオーソドックスな方法のひとつです。以下の要素を重視することで、オーガニックサーチのセッション数を増やしやすくなります。
- キーワード戦略:メインキーワード(セッション数、PV数、メディアなど)だけでなく、関連ワード(アクセス解析、ユーザー数、コンバージョンなど)を盛り込みながら、読者の検索意図を満たすコンテンツを作成します。
- コンテンツのクオリティ:エビデンスや具体例を充実させ、読者が「ここに書いてある情報なら信頼できる」と思えるような専門性とわかりやすさを両立させましょう。
- 内部リンク最適化:関連記事やカテゴリーへのリンクを適切に配置し、検索エンジンに「サイト内の関連性」をわかりやすく示します。同時に、ユーザーが興味のある記事を探しやすくなる効果もあります。
- ページの読み込み速度改善:ページが重いと離脱率が高まり、SEO的にも不利です。画像サイズの最適化やキャッシュ設定などで高速化を図りましょう。
SNS活用で興味を喚起しリピートアクセスを獲得
SNSは拡散力が高く、バイラル効果を期待できます。一方で、一過性の流入で終わってしまう場合も多いため、以下の点に注意しましょう。
- **魅力的な見せ方(ビジュアル、コピーライティング)**画像やタイトルなど、タイムライン上で目を引く要素を工夫して、クリック率を上げる施策を行います。
- 定期的な発信とコミュニケーションSNS経由でのリピーターを増やすには、単発の拡散に頼らず、日々の投稿やユーザーとのやりとりを欠かさないことが大切です。
- キャンペーンやクーポンの活用イベントや限定情報をSNSで先行公開することで、フォロー・リピートアクセスを促進します。
メールマーケティングやプッシュ通知による再訪促進
いったんサイトを訪問してくれたユーザーに対して、定期的に新着コンテンツの情報を届けることで、リピート率(セッション数の底上げ)を高めることができます。
- メールマガジン:興味を持ちそうな記事や特集をピックアップして定期的に配信。
- プッシュ通知:ブラウザ通知やアプリ通知を許可してもらい、新着記事をリアルタイムでアナウンス。
- セグメント配信:ユーザーの興味・行動履歴に合わせてコンテンツを出し分けると、より高い再訪率とエンゲージメントが期待できます。
広告出稿の活用と投資対効果
予算に余裕がある場合、リスティング広告やSNS広告を活用して一気にセッション数を増やす方法もあります。しかし、広告費がかさむ割に成果につながらない可能性もあるため、慎重に運用しましょう。
- ターゲティング精度の向上:年齢、地域、興味関心などを詳細に絞ることで、メディアやビジネスのテーマに合ったユーザーにリーチしやすくなります。
- ランディングページ最適化:広告からの流入先ページがわかりやすく、コンバージョンにつながりやすい構成になっているかを確認します。
- A/Bテストの積極実施:広告の見出しやデザイン、コピーを複数パターンで試し、反応が良いものに予算を集中させる運用方法が効果的です。
データを活かすためのPDCAとチーム体制づくり
セッション数やPV数を含むアクセス解析データは、蓄積していくほど改善の幅が広がります。しかし、「数値を取って終わり」になりがちなのも現実。せっかくのデータを活かすには、継続的に分析・改善を行う体制や仕組みが欠かせません。
PDCAサイクルを回すポイント
PDCA(Plan→Do→Check→Action)は、一般的な業務改善だけでなくWebマーケティングにも応用できます。たとえばセッション数を増やしたい場合、以下のように考えます。
- Plan(計画):
- 目標:セッション数を月間3万から5万に増やす
- 施策:SEOキーワードの拡充、新しい記事フォーマット、SNSキャンペーン など
- Do(実行):
- 計画で立てた施策を実行
- 運用期間や投稿頻度、予算などの具体的なタスク管理
- Check(検証):
- Google アナリティクスのレポートやSNSのインサイトなどをチェック
- セッション数の推移だけでなく、滞在時間や直帰率、コンバージョンの動向も確認
- Action(改善):
- うまくいった点と課題を整理
- 次の施策に活かすために施策内容・予算配分を再検討
この流れを定期的に回すことで、セッション数だけでなく、メディアの全体最適へとつなげられます。
チームや外部パートナーとの連携
オウンドメディアを運営していると、コンテンツ制作、SNS運用、SEO対策、デザイン、技術的な管理など、さまざまな専門知識が必要になります。特に小規模な組織や個人事業主の場合、一人で全部をこなすのは難しいため、外注や専門家への依頼を検討することも大切です。
- コンテンツチーム:ライター、編集者、校正者が協力し、質の高い記事を継続的に提供
- マーケター・アナリスト:アクセス解析や広告運用の専門知識を活かして施策を立案
- デザイナー・コーダー:UI/UXの改善やサイト高速化など技術的側面をサポート
- 外部コンサルタント:全体戦略や指標設定をサポートし、社内にナレッジを蓄積
継続的にセッション数やPV数を伸ばすには、定期ミーティングやスプリント形式での業務進行など、情報共有やコミュニケーションのプロセスを整備することも重要です。
まとめ
本記事では、「セッション数とは何か?」という基本から始まり、PV数やユーザー数との違いを整理しながら、オウンドメディア運営における指標活用のポイントを解説してきました。それぞれの指標は以下のように用途や意味が異なります。
- セッション数:サイトへの訪問のまとまりを数える
- PV数:閲覧されたページ数を計測
- ユーザー数:一定期間内の固有訪問者数
これらの数字を深く理解して使い分けることで、サイトやコンテンツの現状を正しく把握し、次に打つべき施策を明確にできます。たとえば、セッション数の増加を目指すなら、検索エンジン経由やSNS経由など複数の流入源を見直し、魅力的なコンテンツや導線を用意する必要があります。一方で、新規ユーザー数の拡大が課題なのであれば、広告展開やSNSでの発信を強化して認知を広げる施策が重要となります。
また、ただセッション数を増やすだけではなく、最終的にはビジネス成果につなげることが重要です。問い合わせや資料ダウンロードといったコンバージョン指標に至るまでの導線を考慮し、定期的にPDCAサイクルを回して改善を重ねていきましょう。小さな施策の積み重ねがやがて大きな成果を生むはずです。限られたリソースでも、指標をしっかりと理解し、最適な施策を打ち出せば、オウンドメディアのセッション数・PV数、そしてユーザー数を着実に伸ばすことができます。