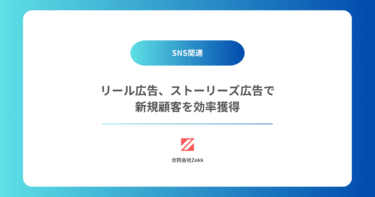あなたは今、企業のデジタルマーケティング戦略を担う担当者として、日々膨大な情報の中から自社が優位に立つ手がかりを探しているかもしれない。特に昨今、TikTokは爆発的なユーザー増加と多様なコンテンツの流通により、若年層を中心にブランド発信の主戦場となりつつある。短尺動画の波に飲み込まれ、競合他社もまた、TikTok上で工夫を凝らしたマーケティング戦略を次々に打ち出している。「なぜあのブランドの動画はバズりやすいのか?」「うちの商品はなぜエンゲージメント率で負けているのか?」──こうした悩みや疑問は、戦略立案を行うあなたにとって日常茶飯事の課題だろう。
しかし、TikTokの競合リサーチは膨大なコンテンツの中から有益な示唆を抽出するだけでなく、そこから自社独自の価値を際立たせる「差別化ポイント」を見いだすプロセスでもある。競合他社が生み出す動画のスタイル、ハッシュタグの選定方法、トレンド曲の使い方、それらを分析し理解することで、自社が新たに打ち出せる戦略的なオリジナルアイディアを創造できるのだ。
本記事では、「TikTok 競合リサーチ」をキーワードに、他社動画を参考に自社がどう差別化戦略を構築するか、そのプロセスとノウハウを徹底解説する。データ分析手法から具体的な制作プロセス改善、成功事例・失敗事例の学びまで、網羅的な情報を提供することで、あなたが自社ブランドを際立たせるための実践的なガイドとなるはずだ。さあ、読み進めることで、競合研究の新たな切り口を掴み、差別化の軸を強固なものにしていこう。
競合リサーチの重要性とTikTok市場の現状
TikTokが動画マーケティングで注目される理由
TikTokは、ユーザーが短時間で魅力的なコンテンツを消費するプラットフォームとして進化している。2020年代に入ってから急速なユーザー増を示し、特にZ世代やミレニアル世代に強い影響力を持つ。スマートフォンで手軽に閲覧でき、アルゴリズム主導のフィードによってユーザーは興味関心に合った動画を次々に発見する。ブランド側からすれば、潜在顧客と短いスパンで多様な接点を持てる「チャンネル」として位置付けることができる。
さらに、TikTokは他のSNSと異なり「フォロワー数」だけでなく、「コンテンツ力」そのものでリーチを拡大できる点が特徴だ。アルゴリズムが優れたコンテンツを優先的に露出するため、無名のブランドであっても、優れた動画がバイラル化すれば一気に認知拡大が可能となる。
他社分析がもたらす戦略的インサイト
競合他社がTikTokでどのような動画を投稿し、どのくらいの頻度で、どんなエンゲージメントを得ているか。そのデータはマーケターにとって宝の山だ。他社の成功パターンや失敗パターンを読み解くことで、自社が踏むべき戦略の道筋が明確になる。
例えば、競合がユーザー参加型のハッシュタグチャレンジで成功しているなら、その要因は何か? 単純に真似るのではなく、その根底にあるコンセプトやユーザーインサイトを理解することで、自社がよりオリジナルな企画を立ち上げる参考となる。また、コメント欄やシェア数から、ユーザーが反応した要素を特定できれば、自社のコンテンツ企画に活用できる。
バイラル動画の背後にある要素
TikTokでバイラル化する動画には、いくつかの共通した要素が存在する。短い中に明確な物語性や驚き、ユーモアや共感できる要素を盛り込み、さらにトレンドの音源や人気ハッシュタグを巧みに利用しているケースが多い。こうした要素を競合分析から抽出し、自社のブランドメッセージと掛け合わせることで、他社とは異なる新たな表現手法を生み出すことができる。
競合リサーチの具体的な手順
競合選定のポイント
まずは「誰を競合とするか」を明確化する必要がある。業界内のトップブランドや、直近で顧客層を奪い合っているプレイヤー、さらには新興ブランドなど、異なる観点から複数の競合をピックアップするとよい。また、海外市場や他業界の事例を参考にすることで、新たなアイディアを得られる可能性もある。
単に「同業他社=競合」ではなく、自社と顧客獲得競争を繰り広げている、もしくは顧客セグメントやブランドポジションが近しい企業を重点的に調べることが重要だ。
投稿頻度・エンゲージメント率・フォロワー推移の分析方法
競合アカウントの投稿履歴を追跡し、その頻度や投稿時間帯、フォロワー増減推移、1投稿あたりの平均的なエンゲージメント(いいね、コメント、シェア)を記録しよう。これにより、競合がユーザーの関心を引く動画をどのくらいのペースで投入しているかがわかる。週に何本投稿しているか、曜日や時間帯に偏りはあるか、フォロワー増加が急激な時期はどんな動画がバズっていたのか──こういった視点から、隠れた成功要因を探り出せる。
また、フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率(エンゲージメント数÷フォロワー数)に注目することで、競合が本質的に「どれほどの熱量を持つファン」を育成しているかを読み解ける。数だけ多くてもアクティブなファンが少ないブランドは、実質的な影響力が限定的といえる。
コンテンツスタイル、トーン&マナー、フォーマット比較
競合動画のテイストや制作クオリティ、映像の長さ、ナレーションやテキスト挿入の有無、そして全体的なブランドイメージとの調和を観察する。ブランドの世界観が統一されたクリエイティブか、常に新しいフォーマットに挑戦しているか、ユーザー参加型企画や商品の使い方を説明するチュートリアル形式が多いかなど、あらゆる角度から分析しよう。
こうした分析は、自社のコンテンツ改善ポイントを洗い出すヒントとなる。例えば、競合が短い動画でも強い印象を残している場合、自社は冒頭3秒で引きつけるアイキャッチを改善する必要があるかもしれない。
ハッシュタグやトレンド曲の活用傾向
TikTokでは、ハッシュタグと楽曲選びがバイラル化の起爆剤となる。競合がどのようなハッシュタグを使い、どの時期に何がトレンドだったかを追跡することで、今後のトレンド予測や自社に合った楽曲・ハッシュタグ戦略が立てられる。
例えば、特定の季節イベント(クリスマス、ハロウィン)や社会的話題(環境問題、スポーツイベント)と関連付けてブランドを訴求している競合の動画は、その切り口やトーン&マナーを参考に、自社独自のコンテンツ企画につなげられる。
自社差別化ポイントの抽出法
顧客ペルソナと独自の価値提案
差別化の鍵は、単なる模倣ではなく「自社の顧客ペルソナ」が求める価値を深く理解することにある。競合リサーチで得た情報から、自社顧客がどのようなコンテンツやメッセージに反応しそうかを推測し、自社が持つ独自の強みと結びつける。
例えば、健康志向の商品を扱うブランドであれば、競合が盛んにフィットネス動画や食事管理のハウツー動画で成功しているかもしれない。その場合、自社は「専門家監修の栄養学的情報」や「顧客コミュニティによる応援メッセージ」を取り入れることで、競合以上に深いエンゲージメントを生むコンテンツを発信できる。
競合との差別化視点:独自コンテンツ開発
差別化とは、「他社がやっていることをより上手くやる」だけでなく、「他社がまだ手を付けていない領域で価値を提供する」ことを意味する。競合リサーチを通じて、まだ利用されていないフォーマット(コマ撮り動画、ARフィルター活用、独自ダンスチャレンジなど)や、未開拓のテーマ(専門性の高い知識共有、ユニークな世界観のストーリーテリング)を見つけ出そう。
こうしたアプローチは、単なる模倣ではなくブランド独自の「磁場」を形成し、ファン層の拡大に繋がる。また、新たなコンテンツ領域を開拓することで、差別化が明確になり、競合との比較においてもブランドの記憶定着度が高まる。
ユーザー参加型キャンペーンの活用
ユーザー参加型キャンペーンはエンゲージメントを飛躍的に高め、ブランドへの愛着を育む有効な手段だ。競合が行ったユーザー生成コンテンツ(UGC)戦略やハッシュタグチャレンジの成功要因を分析し、自社独自のキャンペーン設計に活かそう。
例えば、「商品を使ったクリエイティブなアレンジ方法を投稿する」チャレンジや、「ブランドストーリーをユーザーが代わりに語る」企画など、多面的な切り口が考えられる。重要なのは、ユーザーが参加しやすく、共感しやすいテーマ設定と報酬設計だ。
制作チームのワークフロー改善
競合がなぜスピード感を持ってトレンドに乗っているのか、その背景には効率的なワークフローがあるかもしれない。制作チーム内での情報共有体制、クリエイターやインフルエンサーとの連携手法、迅速なフィードバックサイクルなど、競合研究を通じてプロセス改善のヒントを得よう。
これにより、自社はスピーディかつ高品質なコンテンツを安定的に生産できる体制を整え、結果的に競合を凌駕する存在感を放つことが可能になる。
データ活用と分析ツールの活用
TikTokインサイト機能の活用
TikTok自体が提供するインサイト機能を最大限活用することで、フォロワー属性や動画視聴時間、エンゲージメントのピークタイムなど、競合リサーチで得た仮説を検証できる。自社アカウントのデータを見比べ、競合と異なる点、共通する点を洗い出すことで、改善すべき領域や強化すべきポイントがクリアになる。
インサイトを活用することで、単なる「良いコンテンツ」から「顧客ニーズに的中するコンテンツ」へと進化できる。継続的なデータ追跡を通じて、競合との差別化ポイントがどの程度効果を発揮しているかを定量的に評価することも可能だ。
サードパーティ分析ツール・有料ツールの選定基準
TikTok分析に特化したサードパーティツールや有料分析ツールは、競合調査をより深いレベルでサポートする。例えば、特定アカウントの歴史的なエンゲージメント推移、人気動画のランキング、ハッシュタグや音源のトレンド可視化など、高度な機能を提供するツールが存在する。
ツール選定の際は、価格、機能、操作性、サポート体制、データ精度などを総合的に検討することが重要だ。また、複数ツールを組み合わせることで、より多面的な分析が可能となる。
KPI設計とPDCAサイクルの回し方
競合リサーチから得たインサイトを生かすには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせない。フォロワー増加率、エンゲージメント率、コンバージョン数、クリック率、ブランドリフトなど、ビジネス目標に直結する指標を定め、それに基づいて施策を打つ。
施策実行後は、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し、効果を検証しながら改善策を重ねる。競合リサーチを通じて得た仮説は、テスト施策を通じて検証され、成功すれば強化、失敗すれば修正という循環の中で、マーケティング戦略は研ぎ澄まされていく。
テストマーケティングとスプリットテスト手法
スプリットテスト(A/Bテスト)を用いて、異なる動画クリエイティブや投稿タイミング、ハッシュタグセットを比較検証することで、最適解を見いだせる。競合分析で得たアイディアは、テストマーケティングを通じて自社にフィットするかどうかを迅速に判断できる。
こうしたテストサイクルを組み込むことで、単なる「模倣」から一歩抜け出し、差別化を裏付ける強固なデータを積み上げていくことが可能になる。
成功事例と失敗事例から学ぶ戦略調整
海外ブランドの戦略的TikTok事例
世界的なファッションブランドや飲料メーカーが、TikTok上で斬新なチャレンジやユーザー参加型企画を展開していることは珍しくない。例えば、著名ブランドが独自のダンスチャレンジを立ち上げ、世界中のユーザーが参加・拡散することで一気にブランド知名度が上がったケースがある。
こうした成功事例を分析することで、「なぜその企画が世界中で受け入れられたのか」「どんなメッセージが共通価値となったのか」などを学べる。そこから得た示唆を自社の顧客層やビジネス目標に合わせて応用することで、グローバルな視点を持った戦略立案が可能となる。
競合の失敗パターンと教訓
成功事例だけでなく、失敗事例からも多くを学べる。例えば、頻繁なトレンド追随が逆効果となり、ブランドメッセージが希薄になったケースや、過度に宣伝色の強い動画がユーザーから敬遠された例などがある。
失敗事例の研究は、避けるべき落とし穴を明らかにする。特に競合が取り入れた手法が必ずしも自社に通用するとは限らない点を理解し、流行に流されるのではなく、ブランドアイデンティティに根ざした戦略を構築することが重要だ。
継続的な改善とチーム内部でのナレッジ共有
TikTokはトレンドがめまぐるしく変化するプラットフォームであるため、継続的な改善が不可欠だ。チーム内で学んだ知見をドキュメント化し、定期的なミーティングや社内勉強会を通じて共有することで、全員が最新情報と戦略方針を理解できる。
このような組織的なナレッジ共有は、単一の担当者に依存しない強固なマーケティング基盤を築く。結果として、競合の動きにいち早く対応し、常に自社が一歩先を行く差別化戦略を実行可能になる。
まとめ
本記事を通じて、TikTok競合リサーチの重要性と、その結果得られる戦略的インサイトを活用して自社独自の差別化ポイントを抽出するアプローチを整理した。まず、TikTokがなぜ注目されるのか、その市場特性やアルゴリズムの特徴を理解することで、競合分析の起点が明確になった。
続いて、競合リサーチの手順として、競合選定からエンゲージメント指標分析、コンテンツスタイルやハッシュタグ活用法の比較まで、具体的なステップを紹介した。この分析を通じて、他社が成功している動画の共通要素や、まだ誰も手がつけていない潜在的なテーマ領域を発見できるだろう。
さらに、見つけた示唆を自社顧客ペルソナと独自の価値提案に結びつけ、差別化ポイントを明確化する方法を示した。ユーザー参加型キャンペーンや新規フォーマットの活用、制作ワークフロー改善など、具体的な差別化策が戦略的に生み出せる。これらを裏付けるためには、TikTokインサイトやサードパーティツールを用いてデータ分析を行い、KPI設計とPDCAサイクルを回すことで、効果検証と持続的な改善を実現する。
成功事例・失敗事例から学べば、グローバルな視野で戦略を最適化できるし、逆に避けるべきリスクも見えてくる。結果として、継続的な改善とナレッジ共有を通じ、チーム全体で競合差別化への道を切り拓けるだろう。
今、あなたが行うべきことは、この記事で得た知見をベースに、自社のTikTok戦略を再点検し、次のアクションを明確にすることだ。競合動画がただの「参考例」ではなく、「差別化の起点」に変わる瞬間が、ブランドの新たな成長機会をもたらすのである。



とは?マーケティングの成果を可視化する上で、把握しておきたいCVの基礎知識-375x197.png)